五 謙虚な対応と建設的対話の重要性
当会の弁護士のみなさんは、次のような相談を受けたらどう考えますか?
相談者:「相談にあたって知的障害者にわかるよう合理的配慮をしてもらえますか?」
もしかすると「知的障害者用の合理的配慮なんて特殊な技術は持っていないので無理だ!」と考えて
弁護士:「そんなノウハウないので相談は受けられません」
なんて対応はしていませんか?
できないと最初から思い込むことは傲慢であり、偏見・差別です。
謙虚にまず当事者のお話を聞いてみてください。では次のように言われたらどうでしょうか。
相談者:「私は軽度の知的障害のある24歳です。100万円の羽毛布団の代金を会社から請求されていますので助けてください。ただし難しい言葉は理解できないので、易しく説明してもらえますか?」
話を具体的に考えると違ってきませんか。例えば次のように説明してみたらどうでしょう。
弁護士:「あなたは、悪い会社にだまされたようです」
「だますことはダメなことだから、布団を買いますとあなたが書いたことは無かったことにすると会社に手紙で伝えることができます」
「私は法律に関するお手伝いをする弁護士という仕事をしています」
「あなたの代わりに会社に手紙を出して、会社からのお金の要求をストップするお手伝いができます」
「今までの話を理解できましたか?」
相談者:「はい、易しく話してくれたのでわかりました」
「ただ、忘れやすいので、今の話をメモにしてもらえますか」
今までのやりとりは、何か特別なことでしょうか。
おそらく多くの弁護士が高齢者の方などに、もっと言えば誰に対しても、難しい法律用語を易しく言い換えて説明してきましたよね。
当然なことですが、法律専門職の仕事の本質の一つは、難しい法律の世界を一般の方に分かりやすく伝えながらお手伝いすることです。
「合理的配慮の提供」「建設的対話」という少し難しい用語を聞くと、構えてしまう読者もいるかもしれません。
しかしこれらは私たちの普段の業務の一環もしくは本質に他なりません。
当事者と話し合い(建設的対話をし)ながら、何か法律家としてお役に立てることがないかを率直に探っていってください。きっと、普段の私たちの仕事のやり方の改善にも役に立つはずです。
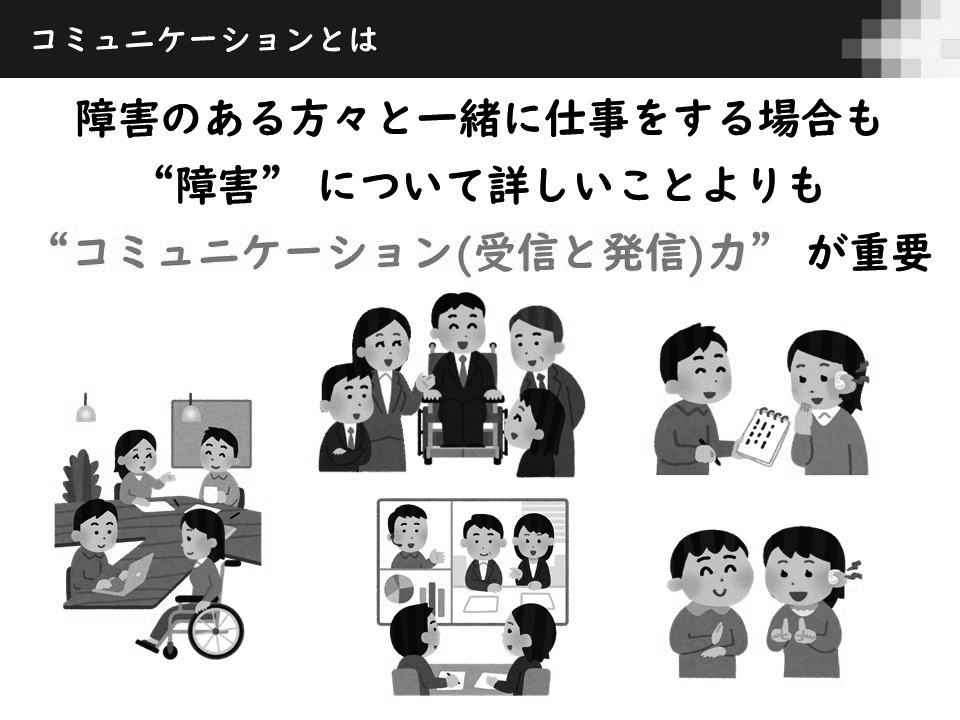
▲箕輪優子さん(後掲インタビュー17頁参照)ご提供スライドより





