紛争解決の流れ
紛争解決の流れ
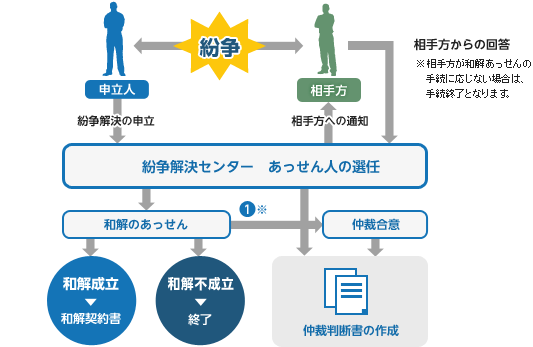
※①申告前に仲裁合意があれば、仲裁手続になります。和解あっせんの途中で仲裁合意が成立すれば、仲裁手続きへ移行することもできます。
- あっせん・仲裁手続きの流れ
 (PDF:35KB)
(PDF:35KB)
書類及び申立手数料の提出
申立書、証拠書類の写しなど必要な書類を東京弁護士会の紛争解決センター事務局に提出して、あっせん手続を申し立てます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
あっせん人の選任
紛争解決センターは、申立を受理すると、事件の特性を考慮してあっせん人を選任します。当事者は、双方の合意の下、あっせん人を指定することもできます。
あっせん仲裁人名簿
相手方への通知
紛争解決センターから、相手方に対し、あっせん申立があったことを通知して、出席を呼びかけます。
相手方からの回答
相手方からあっせん手続に応じるかどうかについて回答が来ます。
相手方があっせんに応じない場合は、手続が終了となります。
あっせん期日の開催
相手方があっせんに応じる場合は、あっせん期日が開かれ、あっせん人がそれぞれの当事者の言い分を聞いた上で解決策について話し合います。
基本的には申立人、相手方同席で話し合いを行いますが、事情により別々に事情を伺うこともあります。
申立人、相手方各々、期日毎に、期日手数料5,500円(税込)がかかります。
①A群書類1点 ②B群書類2点 ③B群書類1点+C群書類1点
A群書類(一点確認で可となるもの)
【官公庁発行の顔写真付・氏名・住所・生年月日記載の身分証明書等】例えば運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート(2020年2月3日迄に発給申請されたもの)、在留カードなど
B群書類(二点確認で少なくとも一点は必須のもの)
【官公庁発行の身分証明書等で氏名・住所・生年月日の記載はあるが顔写真のないもの】例えば健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)
C群書類(二点確認で補完的に使えるもの)
官公庁発行の学生証や社員証(顔写真又は住所の記載が必須)、事件当事者である法人の社員証(顔写真又は住所の記載が必須) 公共料金の領収書(住所・氏名の記載が必須)など和解成立
あっせん期日が1回~数回開催された後、和解成立の場合は和解契約書を作成します。和解成立の場合は、解決額に応じて算出される成立手数料が発生します。
成立手数料の申立人と相手方の負担割合は、当事者の話し合いによるか、あっせん人が決定します。
和解不成立の場合には、あっせん手続は打ち切られ、成立手数料も発生しません。
※申立前に仲裁合意があれば、仲裁手続になります。また、和解あっせんの途中で仲裁合意が成立すれば、仲裁手続へ移行することもできます。

