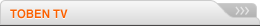
- 新着情報
- 意見書・会長声明
- シンポジウム・講演会
- コラム(セクシュアル・マイノリティ)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
- 性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
- 「結婚の自由を全ての人に」訴訟の進捗状況と世界の同性婚について
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標で4年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 理解増進法とトランスジェンダーに対する誤解
- 全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗報告
- シンポジウム(2024年1月30日開催)参加報告
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標において3年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 同性パートナーの在留資格(2022年12月9日号)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介(2022年12月8日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について(2022年12月7日号)
- 東京弁護士会が今年もPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2022年12月6日号)
- 2022年度セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年12月5日号)
- 職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
- 同性カップルがやがて直面する相続問題(2022年3月3日号)
- セクシュアル・マイノリティと刑事収容施設における課題について(2022年1月21日号)
- 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
- SOGIハラスメント(2022年1月19日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後(2022年1月18日号)
- セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年1月17日号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2021年11月号)
- 国会議員の差別的発言について(2021年6月号)
- セクシュアル・マイノリティを意識した言葉遣い(2021年4月号)
- 東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)
- あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか(2020年9月号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドを受賞!(2019年12月号)
- 「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
- 職場でのカミングアウト(2018年10月号)
- 教育現場とセクシュアル・マイノリティ(2018年4月号)
- 今すぐ取り組める!中小企業のセクシュアル・マイノリティ支援方法(2018年2月号)
- 民間団体・企業向けハラスメント防止研修
- 女性支援ネットワーク会議
- 法教育
- 当委員会が執筆した出版物
- フィンランド視察報告書
経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
2021年5月27日、東京高等裁判所は、経済産業省に勤務する性同一性障害の女性職員が戸籍上は男性であることを理由に職場で女性用トイレの利用を制限されるのは違法ではないとし、使用制限を取り消し132万円の賠償を命じた一審・東京地方裁判所判決を変更しました。日本だけでなく世界的にもセクシュアル・マイノリティの人権保障に関する議論が進んでいる中、今回の東京高裁は、セクシュアル・マイノリティが抱える困難に向き合わず、時代に逆行するような判断となっております。
本事件の争点は多岐にわたりますが、トイレ使用制限に関する点について、第一審では「個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは、重要な法的利益として、国家賠償法上も保護される」「個人が社会生活を送る上で、男女別のトイレを設置し、管理する者から、その真に自認する性別に対応するトイレを使用することを制限されることは、当該個人が有する上記の重要な法的利益の制約に当たる」とし、「生物学的な区別を前提として男女別施設を利用している職員に対して求められる具体的な配慮の必要性や方法も、一定又は不変のものと考えるのは相当ではなく、性同一性障害である職員に係る個々の具体的な事情や社会的な状況の変化等に応じて、変わり得るものである。...当該性同一性障害である職員に係る個々の具体的な事情や社会的な状況の変化等を踏まえて、その当否の判断を行うことが必要である。」として、経済産業省の庁舎管理権の行使に一定の裁量が認められることを考慮しても一定時期以降は国家賠償法上の違法があると判示しました。
これに対し、高裁判決は、「一審原告が主張の基礎とする自らの性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益である」として第一審より法的利益の重要性を減退させたような表現をし、判断枠組みについて国会賠償法1条1の違法性についての最高裁判例を引用し、「事業主の判断で先進的な取組がしやすい民間企業とは事情が異なる経産省」「平成21年7月当時は...性同一性障害者への一般的対応は諸官庁で定まっておらず、指針となる規範や参考となる事例もなく、とりわけ、性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる性自認への対応は全く未知の状況にあった」と行政機関での前例がないこと等を理由として国家賠償法上違法ではないと結論付けました。
これは、自認する性別に即した社会生活を送ることができる法的利益の重要性を軽んじ、対応の遅れている行政機関を擁護する内容と考えられます。 性自認ではなく性的指向についての事件ではありますが、公的施設利用の拒否の違法性が問題となった府中青年の家事件(東京高等裁判所 平成9年9月16日判決。同性愛者の団体からの青年の家の利用申込みを不承諾とした教育委員会の処分を違法であるとして損害賠償を一部認容。)では「平成二年当時は、一般国民も行政当局も、同性愛ないし同性愛者については無関心であって、正確な知識もなかったものと考えられる。しかし、一般国民はともかくとして、都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数者である同性愛者をも視野に入れた、肌理の細かな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されているものというべきであって、無関心であったり知識がないということは公権力の行使に当たる者として許されないことである。このことは、現在ではもちろん、平成二年当時においても同様である。」と判示し、行政機関に対し、セクシュアル・マイノリティに対するきめ細やかな配慮や権利保護を求めていたのに、10年以上経過した現代で行政機関の姿勢として後退を容認する内容です。
また、報道 によれば、河北新報社が行った情報開示請求において、最高裁司法研修所が昨年1月に開いた「複雑困難訴訟」に関する裁判官の研究会で、セクシュアル・マイノリティなどの訴訟を審理する際、司法が権利判断の規範(在り方)や基準を示すことに否定的な意見が相次いでいたとされ、「旧来の価値観を持つ人たちを全く無視したような判断はできない」との指摘や、「(判断の規範は)その事案に限る形にした方が無難」と強調し、打ち立てた規範が絶対的な基準として捉えられないよう「なるべく明文にしない」とする意見も出たとされています。こうした裁判官の認識は、セクシュアル・マイノリティ等の少数者の人権が侵害されている現状にもかかわらず、マジョリティであるシスジェンダーを指すのであろう「旧来の価値観を持つ人たち」のために司法的判断を控えているものであり、人権救済の最後の砦たる裁判所の役割を果たさないあるまじき事態です。
第一審・控訴審原告は、最高裁判所に上告中ですが、最高裁判所において適切な判断がなされることを強く望むとともに、行政及び司法機関において、セクシュアル・マイノリティに対する不当な差別や偏見がなくなるよう、当委員会では今後も活動を続けていきます。

