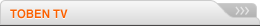
- 新着情報
- 意見書・会長声明
- シンポジウム・講演会
- コラム(セクシュアル・マイノリティ)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
- 性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
- 「結婚の自由を全ての人に」訴訟の進捗状況と世界の同性婚について
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標で4年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 理解増進法とトランスジェンダーに対する誤解
- 全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗報告
- シンポジウム(2024年1月30日開催)参加報告
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標において3年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 同性パートナーの在留資格(2022年12月9日号)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介(2022年12月8日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について(2022年12月7日号)
- 東京弁護士会が今年もPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2022年12月6日号)
- 2022年度セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年12月5日号)
- 職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
- 同性カップルがやがて直面する相続問題(2022年3月3日号)
- セクシュアル・マイノリティと刑事収容施設における課題について(2022年1月21日号)
- 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
- SOGIハラスメント(2022年1月19日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後(2022年1月18日号)
- セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年1月17日号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2021年11月号)
- 国会議員の差別的発言について(2021年6月号)
- セクシュアル・マイノリティを意識した言葉遣い(2021年4月号)
- 東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)
- あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか(2020年9月号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドを受賞!(2019年12月号)
- 「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
- 職場でのカミングアウト(2018年10月号)
- 教育現場とセクシュアル・マイノリティ(2018年4月号)
- 今すぐ取り組める!中小企業のセクシュアル・マイノリティ支援方法(2018年2月号)
- 民間団体・企業向けハラスメント防止研修
- 女性支援ネットワーク会議
- 法教育
- 当委員会が執筆した出版物
- フィンランド視察報告書
性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
性同一性障害者の性別の取扱いの変更に関する法律(以下「特例法」といいます。)は、「性同一性障害者」(※)が法令上の性別の取扱いを変更するための要件として、次の5つの要件を定めています(3条1項)。
① 18歳以上であること
② 現に婚姻をしていないこと
③ 現に未成年の子がいないこと
④ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑤ その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
最高裁判所は、2023年10月25日、男性から女性への性別変更の審判を求めた事案において、次のように指摘し、要件④(生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること)は憲法に違反し無効であると判断しました。
・憲法13条は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障している
・性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益である
・医学的知見の進展により、性同一性障害者が必要な治療を受けたか否かは手術を受けたか否かによって決まるものではなくなった
・要件④は、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、または性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものである
そして、最高裁判所は、要件⑤について審理させるために、広島高等裁判所に差し戻しました。
報道によれば、2024年7月10日、差し戻しを受けた広島高等裁判所は、要件⑤について、「手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるをえない」、「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘し、当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから性別変更を認めた、ということです。
従前、女性から男性への性別取扱い変更審判では、ホルモン療法によって手術をすることなくその要件⑤を満たす場合がある一方、男性から女性への性別変更審判を求めるには通常手術が必要となると考えられていました。
この広島高等裁判所の決定は、男性から女性への性別変更審判を求める場合でも、ホルモン療法によって手術をすることなくその要件⑤を満たす場合があることを示したものといえます。
しかし、たとえば、持病のためにホルモン治療を受けることができない場合はどうでしょうか。また、ホルモン治療は、生涯又は長期にわたり継続し、身体の不可逆的な変化がありうるほか、様々な副作用のリスクを有することが指摘されています。それでも、ホルモン治療をしなければ、性別変更できない、とすることは憲法上許されるでしょうか。
上記最高裁判所決定の三浦裁判官、草野裁判官、宇賀裁判官の各反対意見は、要件④のほか要件⑤も違憲とするものですので、ぜひお読みいただき、上の点について考えてみていただけたらと思います。
最高裁判所令和5年10月25日決定:
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/092527_hanrei.pdf
東京弁護士会は、2022年3月23日付「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の『現に未成年の子がいないこと』の要件に関する意見書」などにより、特例法の要件緩和を訴えてきたところですが、今後も、セクシュアル・マイノリティの人権擁護のための活動を続けていきます。
※...世界保健機関(WHO)が策定する国際疾病分類の第11改訂版(ICD-11)において、「性同一性障害」は、障害ではなく、「性の健康に関する状態」に分類され、名称も「性別不合」に変更されましたが、ここでは、法令上の用語として「性同一性障害者」の語を用います。特例法2条は、「性同一性障害者」を生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものと定義しています。

