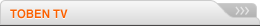
- 新着情報
- 意見書・会長声明
- シンポジウム・講演会
- コラム(セクシュアル・マイノリティ)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
- 性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
- 「結婚の自由を全ての人に」訴訟の進捗状況と世界の同性婚について
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標で4年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 理解増進法とトランスジェンダーに対する誤解
- 全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗報告
- シンポジウム(2024年1月30日開催)参加報告
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標において3年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 同性パートナーの在留資格(2022年12月9日号)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介(2022年12月8日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について(2022年12月7日号)
- 東京弁護士会が今年もPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2022年12月6日号)
- 2022年度セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年12月5日号)
- 職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
- 同性カップルがやがて直面する相続問題(2022年3月3日号)
- セクシュアル・マイノリティと刑事収容施設における課題について(2022年1月21日号)
- 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
- SOGIハラスメント(2022年1月19日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後(2022年1月18日号)
- セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年1月17日号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2021年11月号)
- 国会議員の差別的発言について(2021年6月号)
- セクシュアル・マイノリティを意識した言葉遣い(2021年4月号)
- 東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)
- あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか(2020年9月号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドを受賞!(2019年12月号)
- 「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
- 職場でのカミングアウト(2018年10月号)
- 教育現場とセクシュアル・マイノリティ(2018年4月号)
- 今すぐ取り組める!中小企業のセクシュアル・マイノリティ支援方法(2018年2月号)
- 民間団体・企業向けハラスメント防止研修
- 女性支援ネットワーク会議
- 法教育
- 当委員会が執筆した出版物
- フィンランド視察報告書
シンポジウム(2024年1月30日開催)参加報告
東京弁護士会は、2024年1月30日、「『外国人・障害者・LGBTQ+、って怖いからアパート貸せません。』これって違法じゃないんですか、弁護士さん?! ~だれも排除されない社会のために必要なことは何か~」と題して、シンポジウムを開催しました。
性の平等に関する委員会委員が担当したLGBTQ+事案の報告では、
● 住民票の住民票の性別の記載と外見との間に齟齬があることを理由に賃貸物件を借りることを拒否された事例があること
● 同性カップルが、その関係性を考慮されることなく、同性だからという理由で「二人入居可」という物件に入居できず、結果的に異性カップルと比べて不利益を被っている事例があること
● セクシュアル・マイノリティ当事者の中には、不動産業者へのセクシュアリティの開示やそれを余儀なくされる可能性がある不動産業者へのアクセス自体に抵抗を感じている方が少なくないこと
● 東京都では「LGBT等」を住宅確保要配慮者に指定しており、行政の認識としても住宅確保が難しいという認識であること
などの事実をもとに、セクシュアル・マイノリティ当事者が賃貸物件を借りにくい現状について、報告しました。
なお、セクシュアル・マイノリティが感じる困難としては、今回取り上げたもののほか、女性同士のカップルやトランスジェンダーの経済力の問題に起因して、又は、外国人である同性カップルなどセクシュアリティとは別の属性との複合的な原因により、不動産が借りにくいというケースもあると思われます。
今回のシンポジウムでは、外国人や障害者が感じる住居確保の困難に関する事案や裁判例、法令の紹介なされ、様々なマイノリティといわれる人々にとって、住居を確保することが社会的に困難である現状を改めて認識しました。また、先進的な取組みを行っている不動産業者による活動の共有では、実際的な工夫を教えていただきました。
病気になったり、年を重ねたりすることを考えれば明らかですが、誰しも、マイノリティになることや、それに関連して生活の様々な場面において社会的な困難に直面することがあり得ます。このため、他者としてのマイノリティを保護しようという話ではなく、私たち自身がどう扱われたいかという問題として考えていきたいと思います。
だれもが生きやすい世の中を、一緒につくっていけたらうれしいです。

