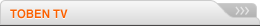
- 新着情報
- 意見書・会長声明
- シンポジウム・講演会
- コラム(セクシュアル・マイノリティ)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
- 性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
- 「結婚の自由を全ての人に」訴訟の進捗状況と世界の同性婚について
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標で4年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 理解増進法とトランスジェンダーに対する誤解
- 全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗報告
- シンポジウム(2024年1月30日開催)参加報告
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標において3年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 同性パートナーの在留資格(2022年12月9日号)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介(2022年12月8日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について(2022年12月7日号)
- 東京弁護士会が今年もPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2022年12月6日号)
- 2022年度セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年12月5日号)
- 職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
- 同性カップルがやがて直面する相続問題(2022年3月3日号)
- セクシュアル・マイノリティと刑事収容施設における課題について(2022年1月21日号)
- 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
- SOGIハラスメント(2022年1月19日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後(2022年1月18日号)
- セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年1月17日号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2021年11月号)
- 国会議員の差別的発言について(2021年6月号)
- セクシュアル・マイノリティを意識した言葉遣い(2021年4月号)
- 東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)
- あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか(2020年9月号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドを受賞!(2019年12月号)
- 「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
- 職場でのカミングアウト(2018年10月号)
- 教育現場とセクシュアル・マイノリティ(2018年4月号)
- 今すぐ取り組める!中小企業のセクシュアル・マイノリティ支援方法(2018年2月号)
- 民間団体・企業向けハラスメント防止研修
- 女性支援ネットワーク会議
- 法教育
- 当委員会が執筆した出版物
- フィンランド視察報告書
職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
厚生労働省作成の「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~」(令和元年度)によると、LGBTQ等のセクシュアル・マイノリティの人権に配慮した取組みについて企業の関心は高まりつつあるものの、実際の取組みは進んでおらず、実施できている企業は一部の企業に限られるとされています。
職場における取組事例として、セクシュアル・マイノリティに関する方針の策定、就業規則への差別禁止等の明記、研修の実施、休暇・休職や支給金その他福利厚生面において同性パートナーを異性パートナーと同様に扱う人事制度の変更等が存在します。これらの取組みをひとつでも実施していることで、セクシュアル・マイノリティの方が「存在するもの」として会社がその企業活動を行っているというメッセージになり、セクシュアル・マイノリティ含め多くの従業員の職場環境における心理的安全の確保等につながります。当コラムでも以前、大企業に限らず中小企業でも実施できるセクシュアル・マイノリティ支援方法をこちらでご紹介しましたのでぜひご参考にしていただければと思います。
このような取組みのひとつとしてトランスジェンダーの方向けの性別移行ガイドの作成が挙げられます。トランスジェンダーの方が性自認に応じた性別で働くことを望んだ場合に、本人、ならびに上司および人事担当者等の関係者がどのように対応すべきかを記載したガイドです。自認する性別で生きるということは個人の尊厳にかかわる極めて重要な事項で、それが実現できないことにより日々の職場生活の中で耐えがたい苦痛を感じている方が存在します。しかし、トランスジェンダーに関する理解がまだ十分ではない現状では、多くの場合、職場における性別移行は本人にとって非常に勇気が要る決断となります。性別移行ガイドがあることで、本人は自らがまず何をすれば良いのか知ることができ、また会社の対応も予測できるので、安心して性別移行を行うことができます。
性別移行ガイドは会社の実態に合わせてその内容が検討されるべきものですが、一例として以下のような項目を盛り込むことが考えられます。
【本人向け】
| 項目 | ポイント等 |
| 性別移行前の相談先 | ・ まず誰に相談すれば良いか明確にする ・ 上司との関係性は様々であるため人事担当者を含め複数の選択肢があることが望ましい |
| 外見の移行 | ・ 服装・髪型等に関する社内規定がある場合は当該規定との関係性 ・ 移行が分かりやすく表れる場面なのでタイミングについての協議等(ただし、外見の移行を制限するものであってはならない) |
| トイレ・シャワー・更衣室・寮等性別に対応した施設の利用 | ・ 施設状況に応じて現実的かつ本人に負担が少ない方法を検討する |
| 通称名の使用 | ・ 戸籍上の名の変更がない場合における通称名使用方法および使用可能範囲等 |
| 医療・休暇 | ・ 性別移行に関連してホルモン投与、手術等について、会社として利用可能な制度、休暇の取得方法等 ・ 健康保険被保険者証に関する手続(①性別取扱いまたは名の変更がある場合、②性別取扱いの変更はないが性別表記を被保険者証裏面記載へ変更希望する場合)等 ・ 健康診断を社内で性別に応じて集団実施する場合の配慮、医療機関との連携等 |
| 長期出張・転勤 | ・ 出張・転勤先で必要な治療を受けられない場合の対応 ・ 出張・転勤先の職場環境の必要に応じた調整 |
【上司・人事等関係者向け】
| 項目 | ポイント等 |
| 初期対応 | ・ 本人から相談を受けたときの受け止め方、対応方法 ・ 共有範囲について本人と特に十分に確認する |
| 本人のプライバシーへの配慮 | ・ アウティングにならないように情報の取扱いには十分に注意する |
| 社内外への対応 | ・ 性別移行後、本人の希望を前提に、社内各部署への共有範囲およびタイミングを検討 ・ 必要な場合、取引先等への連絡 ・ 雇用管理上の性別情報の管理の徹底 ・ 社内外への改めての啓もう活動が必要な場合の案内等 |
なお、性別移行といっても必ずしも戸籍上の性別変更を伴うものではないことに注意が必要です。日本では、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により、性別適合手術が法令上の性別取扱いおよび戸籍上の性別記載の変更要件とされています。しかし、性別取扱い変更等のために、身体的・経済的負担が大きい性別適合手術を強制していること自体深刻な問題となっています。全てのトランスジェンダーの方が性別適合手術を望んでいるわけではないこと、たとえ望んだとしても手術を受けることが可能とは限らないこと、その強制は重大な人権侵害であることを企業は認識しておかなければなりません。
性別移行ガイド作成後も、硬直的にガイドを適用するのではなく、本人との十分な対話を通じての対応が望まれます。また、制度を作って終わりではなく、繰り返し社内で啓もうおよび周知していくことで、より実体を伴ったものにしていくことが大切です。

