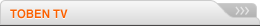
- 新着情報
- 意見書・会長声明
- シンポジウム・講演会
- コラム(セクシュアル・マイノリティ)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 性別の取扱いの変更要件の一部を無効とした最高裁令和5年10月25日決定について
- 性的指向及び性自認に関する基本理念、職員向けガイドライン
- 「結婚の自由を全ての人に」訴訟の進捗状況と世界の同性婚について
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標で4年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 理解増進法とトランスジェンダーに対する誤解
- 全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗報告
- シンポジウム(2024年1月30日開催)参加報告
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介
- 東京弁護士会がPRIDE指標において3年連続でゴールドとレインボーをW受賞しました!
- 同性パートナーの在留資格(2022年12月9日号)
- 東京三弁護士会多摩支部の取組みのご紹介(2022年12月8日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の進捗について(2022年12月7日号)
- 東京弁護士会が今年もPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2022年12月6日号)
- 2022年度セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年12月5日号)
- 職場における性別移行ガイド(2022年7月28日号)
- 同性カップルがやがて直面する相続問題(2022年3月3日号)
- セクシュアル・マイノリティと刑事収容施設における課題について(2022年1月21日号)
- 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について(2022年1月20日号)
- SOGIハラスメント(2022年1月19日号)
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後(2022年1月18日号)
- セクシュアル・マイノリティ週間の開始にあたって(2022年1月17日号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドとレインボーをW受賞しました!(2021年11月号)
- 国会議員の差別的発言について(2021年6月号)
- セクシュアル・マイノリティを意識した言葉遣い(2021年4月号)
- 東京都足立区議会における区議会議員による性的少数者に対する差別発言について(2021年1月号)
- あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか(2020年9月号)
- 東京弁護士会がPRIDE指標でゴールドを受賞!(2019年12月号)
- 「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
- 職場でのカミングアウト(2018年10月号)
- 教育現場とセクシュアル・マイノリティ(2018年4月号)
- 今すぐ取り組める!中小企業のセクシュアル・マイノリティ支援方法(2018年2月号)
- 民間団体・企業向けハラスメント防止研修
- 女性支援ネットワーク会議
- 法教育
- 当委員会が執筆した出版物
- フィンランド視察報告書
「SOGIハラ」をなくそう(2019年6月号)
「セクハラ」、「パワハラ」といった言葉は、近年、誰もが知る言葉となりました。今回は「SOGIハラ」を取り上げたいと思います。
「SOGIハラ」はSexual orientation and gender identity(性的指向及び性自認)についてのハラスメントのことで、「ソジハラ」または「ソギハラ」と読みます。
性的指向とは、自身がどの性の人に恋愛感情を抱くかという、感情の方向性のことをいい、性自認とは、自身がどの性に属しているかという認識のことを言います。
こういった性的指向や性自認について嫌がらせを行うことを「SOGIハラ」と言います。
例えば、「ホモ」「レズ」などと言って相手を侮蔑することはもちろんのことですが、「あの人、しぐさがホモっぽい」などと嘲笑することもSOGIハラです。
また、性自認は男性の方に対して、戸籍や身体上の姓が女性であることをもって、職場で女性の服装を強要することもSOGIハラに該当しますし、本人の了承を得ずにその者が公にしていない性自認や性的指向を暴露すること(アウティング)もSOGIハラです。
普段の会話の中や飲み会の席等で、面白半分で「ホモ」や「レズ」などと聞いたことはないでしょうか。SOGIハラに該当するかは、その他のハラスメントと同様に、それを受けた人が「嫌だ」と思ったかどうかで判断されます。先ほどの例でいくと、「ホモ」や「レズ」と言った本人は何とも思っていなくても、それを聞いた人の中で、不快な思いをした人がいれば、それはSOGIハラです。
いくつか例をあげました。確かに、セクシュアルマイノリティがSOGIハラの被害を受けやすい傾向にはありますがSOGIハラはセクシュアルマイノリティだけの問題ではありません。誰しもが有している性的指向と性自認に関わる問題です。
現在、男女雇用機会均等法を受けて作成された「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」においては、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュアルハラスメントに該当することが明示されたに止まり、SOGIハラについての言及はありませんでした。一方で、国家公務員を規律する人事院規則においては、その運用(『人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について』)において、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含む、性的な関心や欲求に基づく言動がセクシュアルハラスメントに該当しうるということを定めています。
このように、現状では官民で少し差はありますが、本年5月29日に、職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける関連法が成立しました。併せて、今後策定される「パワハラ対策指針」にSOGIハラの防止も盛り込まれることになりました。
SOGIハラがこの指針の中でどのように規定されるかはまだわかりませんが、その内容にかかわらず、みんなが互いの個性を尊重しあって、SOGIハラをなくすという意識が非常に大切です。
まずは、自分自身が意識し、次は自分の周囲の人にという形で、SOGIハラをなくすという意識が広がっていくと、みんなにとってより居心地のいい社会ができるのではないでしょうか。

